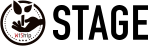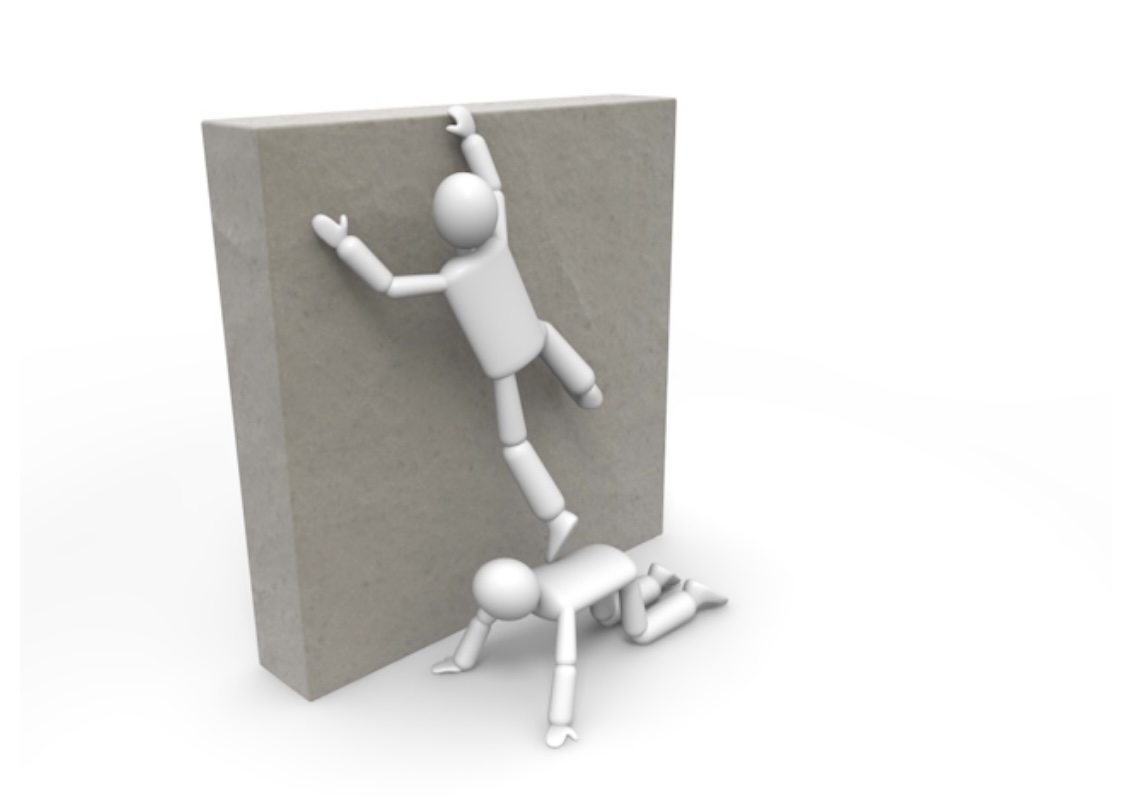塾の先生は生徒と保護者に一人前にしてもらってる(前編)
「塾の先生」という仕事。
一見、簡単そうに見えますが(笑)、なかなか難しいですよね?
本気でやっている人は、この難しさを痛感されていることでしょう。
でも、我々はいろいろな生徒と格闘していくことで、「一人前の塾の先生」になっていくのです。
今日はそんな話。
あっ、これについては私がごちゃごちゃ書くのではなく、久々にタヌーキさんと我利勉さんに登場してもらいましょうか。
武太陽子(ムタイヨウコ)が一人前の塾の先生になったあのシーンから。
【「個別指導の神様が降りてきた!」の物語より】
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・
第43話. 「一人前の塾の先生になるということ」の巻
日曜日。
休みにも関わらず武太陽子は朝から教室に行き、テスト対策プリントを作り終えてから、少し遅れて約束の場所に向かった。
今日は大学時代の友人とプチ同窓会だ。
「皆、遅れてごめんね~」
「陽子、遅いじゃない。もう始めちゃってるよ」
「陽子、最近、全然連絡くれなかったけど、元気にしてたの?」
「うん、元気は元気なんだけど、仕事がすっごく忙しくて……」
「ほんと仕事ばっかりなんだから、もぉ~。でも、仕事って、たしか塾の先生だったよね?」
「で、何の教科を教えてるの?」
「何の教科って……う~ん、何でも教えてるというか、何も教えていないというか。今、教室長っていう、子ども達やアルバイト講師達を管理する仕事なの」
「凄いじゃない!入社一年目で。じゃあ、お給料は一杯もらってるんでしょ?」
「そんなにもらってないよ。このくらい」
武太が示した数字に、友人たちは一瞬顔を見合わせた後、口々にこう言った。
「まじでー!嘘でしょー!」
「そんなに少ないのー!?あり得ないって!」
「あなた、騙されてるんじゃない?少なすぎるわよ」
「えっ。えっ。じゃ、じゃあ、みんなどれくらい貰ってるの?」
武太以外の全員は、いわゆる「いい会社」に勤めていた。
その差は歴然だった。
「ちょっと真剣に考えなきゃダメよ。そんな安月給で、重い責任を押し付けられて、しかも思いっきりこき使われて。バカみたいだと思わない?何か、最近の陽子ってダサいよ」
「そうよ。陽子は才能があるんだから、もっといい会社に入って、仕事に見合った給料も貰って、もっと人生を楽しんだほうがいいよ」
「ほんと、いいように利用されてるんだから。完全にブラック企業じゃん。きっとその塾長って、自分の利益のために、陽子を道具のように使ってるのよ!」
「で、でも、とってもいい人で……仕事も充実してるし……」
「ほんと、陽子はお人好しね!私、本で読んだよ。そうやって、やりがいだの成長だのを口実に、当然のように激務を押し付けるのを『やりがいの搾取』って言うんだってさ。悪いこと言わないから、ちゃんと仕事と自分の人生考えなよ」
仕事の話はそこまでで、そんなに長いものではなかったが、武太の中にはモヤモヤしたものがズシリと残った。
それから三日後のことである。
「武太先生!」
「……」
「武太先生ってば!」
「あっ、はい!すみません!」
武太は月曜からずっとこの調子だ。
「体調でも悪いの?」
「たいしたことないんですけど、ちょっと微熱が続いてて……でも、大丈夫ですから」
「それならいいけど……ところで、今週末のテスト対策ゼミ担当講師って手配してるよね?」
「あっ、すみません。まだです。今日中には手配します」
「ちょっと遅いよ。皆、予定入れちゃってるかもしれないでしょ。もぉ~、しんどくても、やるべきことはしっかりやらなきゃ。絶対に今日中に連絡して!あっ、それとね、生徒数も90名を超えてなかなか大変な人数になってきたよね。もう少し私も現場に入るよ」
その瞬間、武太の目つきが変わったことに、私は気付けずにいた。
頑なにそれを拒んだかと思うと、この日以来ムキになったように朝早くから夜遅くまで働き始めたのだ。
しかし相変わらず表情には陰りがあり、私はそれが気になって仕方がなかった。
そしてその不安は形となって表れ始める。
今まで百発百中だった入会面談でも精彩を欠き、三回連続で入塾を逃すという本来の武太ならあり得ない結果を招いてしまったのだ。
「武太先生、本当にどうしちゃったの?」
「あっ、面談の失敗の件ですよね。すみません」
「いや、それは仕方がないんだけど、とにかく元気がないから心配で。それに……」
「我利先生、はっきり言ってもらっていいですよ」
私の言葉を制して、武太は言った。
明らかに、普通ではない様子だ。
「私じゃ頼りないから、教室長を任せられないって思っているんじゃないですか!」
もちろん、そんなことは思っていない。
「いいですよ。ダメならダメってはっきり言ってください」
「だから、そんなこと思ってないって!」
「もういいです!我利先生の顔を見てたら分かりますから!」
「ちょっと!武太先生、落ち着きなよ!」
「私だって、自分なりに必死に頑張って来たんです。でも、でも……今、どうしてもうまくいかなくて………」
武太は目に涙をためながら席を立ち、教室の外に飛び出して行った。
一人教室に残された私は、頭を抱える。
タヌーキの言っていたのはこういうことか……その日、武太は教室に戻って来なかった。
翌日。
携帯メールに届いたのは、武太からの「休ませてほしい」という連絡だった。
私は慌てて返信したが、メールは一切返ってこない。
電話にも応答がなかった。
このまま武太は来なくなるんじゃないだろうか……私は、絶望的な気分になっていた。
こういうときに限ってタヌーキは現れない。
「もう少し様子を見るしかないか……」
その時、どこからとなく声がした。
「様子なんて見てたらあかん。今、動くんや。あの娘な、この前のプチ同窓会で、皆から仕事のことや給料のことを色々言われてて、惨めな想いをしとったで。今まで必死に頑張って来たのに、可哀想にな。ジブン、救ってやらなあかんで。だから、今から行くんや。武太ちゃんの家まで行くんや。そこで、ちゃんと話をするんや。ええか、あの娘の人生を一緒に真剣に考えてやるんやで!」
「えっ?タヌーキさん?」
タヌーキの姿はどこにもない。
しかし、私は分かっていた。これがタヌーキらしい愛情表現なんだ。
よし、行こう。ありがとう、タヌーキさん。待ってろよ、武太先生……。
私は車を飛ばして、武太の家へ向かった。
武太は驚いていたようだったが、どうにか外に連れ出し、近くの公園へ向かう。
「武太先生、体調はどう?」
「正直あまり優れないんですけど……でも、それより私、やっぱりこの仕事は向いていないんじゃないかと考えていて……私には子ども達の人生の一端を背負うのも、会社の将来を背負うのも、荷が重い気が……」
「武太先生、ごめんな」
武太は「えっ?」という顔をして、こちらを見る。
「な、何で我利先生が謝るんですか?」
「謝るのは当然だ。武太先生は責任感が強くて、凄くできる人だから、私は安心しきっていて、全然、武太先生の苦しみを分かってあげられてなかった」
「いえ、そんなことないです。我利先生にはいろいろ助けてもらって……」
「でも、凄いプレッシャーを感じてきたでしょ?」
「……」
「いつ潰れるかも分からないこんな塾に入社してくれて、僕の家族が路頭に迷わないためにも必死に目標数字を追いかけてくれて、宇島先生の入社の件も一手に背負って、今も必死に頑張ってくれてる。それなのに、たいした給料も払ってあげられてなくて、感謝の言葉もろくにかけてあげられてなくて……本当にごめん。きっと、この前の同窓会でも惨めな想いをさせてしまったんだろうと思うと、本当に申し訳なくて……」
私は、泣いていた。
「我利先生……」
「武太先生は、この一年、苦しいことも辛いことも一杯あったけど、決して諦めずに頑張ってくれた。そのことは私が一番分かってる。でも、そんな武太先生が、『仕事ばっかりして』とか、『安い給料で』とか、そんなふうに言われたとしたら、私は悔しくて、悔しくて」
「えっ?我利先生、私が友達に何を言われたか知ってるんですか?」
「詳しくは知らないけど、だいたい分かるよ。でもね、世の中、何でもかんでも損得を絡めて物を言う人もいるかもしれないけど、自分の会社の不甲斐なさを棚に上げて言わせてもらうなら、それはおかしいと思う。どんな仕事だろうと、その人が納得して、頑張ってやっているんだったら、絶対にバカにしちゃいけない。ましてや、友達ならなおさらだ!そんなの本当の友達じゃないよ!真面目な話、武太先生は絶対にこの仕事は向いていると思う。面談する生徒や保護者をすぐに元気にできる、そんな力を持った人を僕は今まで見たことがない。これは武太先生が持って生まれた才能だ。だから、私のためでもなく、塾のためでもなく、自分のためにこの仕事は続けて欲しい。そうじゃなきゃ、勿体無いよ。武太先生には大きな大きな可能性があるんだから、今、諦めちゃだめだ!」
「でも私……私、どうていいか分からなくて……」
「何も考えなくていい。とにかく、一緒に頑張ろう。どんなことがあっても、僕と一緒に頑張ろう。だから、明日から元気に塾に来て欲しい」
「そ、それは……」
「それに、実は明日、武太先生を凄く慕ってる大松さんの面談が入ったんだ」
「えっ?大松さんの面談が?どうしてですか?」
「お母さんから電話があってね。最近、本人のやる気が全然なくて、塾を続けるかどうかも含めて相談したいっていう話があったんだ。だから武太先生、明日は絶対に塾に来てほしい。あの子の面談をできるのは武太先生しかいないよ」
「でも、我利先生、今の私じゃ……」
「大丈夫、武太先生ならできる。僕は武太先生を信じて待ってるから。絶対に待ってるから」
それだけ話して、私は武太の下を立ち去った。
※続きは明日(^_-)-☆
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田でした![]() 。
。