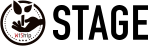その時、どこからともなく声がした。
「ジブンら、ほんまあかんわ。しょうもなさ過ぎやわ。」
「えっ?今、誰かしゃべりました?」
「いや。」
「じゃあ、今のは空耳?」
「空耳やない。」
「あっ!やぱり、誰かいますよ!」
「確かに!誰だ!」
「わしや。わしやがな。」
「あっ、その声はタヌーキさん?」
「そうや、我利ちゃん、ちょっとご無沙汰やったな。」
皆が一斉に声のする方を見た。
そこには窓から顔を出しているタヌキのような姿があったのだ。
「ぎゃー!!タヌキがしゃべってる!!」
我利以外の社員達は一斉に叫んでいた。
「誰がタヌキやねん。失礼な奴らやで。まあ、社長が失礼やと、社員も失礼になるちゅう典型的なダメ組織のパターンやで。」
「我利先生、何なんですか、このタヌキは?」
「だから、タヌキ違うっていってるやん。ボケ。」
「皆、落ち着いてくれ。このタヌキはタヌキじゃない。タヌーキなんだ。」
「えっ?いったい何を言ってるんですか?」
「あっ!まさか、我利先生が前に言っておられた神様ですか?」
営業本部長の下村が言った。
「うん…。」
「か、か、か、神様!!!」
またまた、社員達が一斉に叫んだ。
「ちょっと、中に入らせてもらうで。よいしょっと!」
「あなたは神様…なんですか?」
「おお、武太ちゃん、久しぶりやな。」
「えっ?私、会ったことありました?」
「いや、ない。今から十二年前くらいに、わしが勝手に見てただけやからな。」
「ん?見てた?…ぎゃー!!」
「何やねん、でかい声出しよってからに。」
「見てたって、それ、私をストーカーしてたってことでしょ?」
「違うわい。ジブンみたいな小娘に興味ないわ。」
「はあ?小娘ですって!」
「まあまあ、武太先生、落ち着いて、落ち着いて。このタヌーキさんは、十二年前、“個勉塾”を立ち上げた時に、陰で私を助けてくれていた神様なんだ。だから、武太先生のことも知っているってこと。」
「そうなんですか。」
「まあでも、武太ちゃんは、相変わらず、威勢のいい子やで。アハハハ。」
「威勢のいい子…ですか…。」
「それに、ジブン、相変わらず、よう頑張ってるみたいやな。結婚して、ガキんちょもできて、それでもバリバリ仕事してて、偉いと思うで。」
「あっ、はい…。有り難うございます。」
「それに比べて我利ちゃんや。」
「はい?」
「我利ちゃんも頑張ってへんことはないけど、十年以上経った今でも、オーラもないし、ブサイクやし、何かイマイチなんやなあ。」
「すみません…。」
「今回もキーツネの罠にまんまとハマってこの様やからな。」
「あっ、はい…。」
他の社員達はこのやり取りを呆然と見守るしかなかった。
「おお、おお、ジブンら、何をぼーっとしてんねん。頭が高いと違うか?わし、神様やで。」
そう言われても、誰も頭を下げようともしなかった。
「我利ちゃん、日頃、社員達にどんな教育してんねん。ほんまに。」
「あっ、すみません!ほらっ、皆、挨拶して。」
社員達は順番に自己紹介をして、タヌーキに挨拶をしていった。
「おお、悪いな、自己紹介までしてもろうて。でも、誰が誰かさっぱり覚えられへん。皆、ショボい顔してるから、全部、ウ〇チに見えるわ。アハハハ。」
「我利先生、何なんですか、この失礼なタヌキ…いや、神様は。」
「ごめん、ごめん。本当に失礼な神様なんだけど、根はいい人だから。」
「だから!!“人”違うって言ってるやん。わし、“神様”やって!」
「あっ、すみません、すみません。」
我利はタヌーキに謝り、社員にも謝り、右往左往していた。
「それにしても、我利ちゃん、笑わしてくれるわ~。さっきも、“申し訳ない。全て私の責任だ”なんて言ってるさかい、思わず窓の外で爆笑してしもうたわ。」
「何がおかしいんですか?」
「だって、そうやん。社長なんやから全責任があるのは当たり前やん。それを神妙な顔をして、真面目にしゃべってるさかい、笑うしかないやろ。うひゃうひゃ…今、思い出しても笑けるわ。」
「・・・。」
「それから、そこにいるジブンら、何してんねん。状況が悪くなったからといって、犯人探しかいな。」
「別に犯人探しというわけでは…。」
「いやいや、そうなってるやん。あいつが悪い、こいつが悪い、あいつがもっと頑張れば、こいつがもっと頑張れば、あいつのせいで、こいつのせいで、そんな話ばっかりしてるやん。犯人探しをしているような組織は終わってるわ。」
「・・・。」
「ええか、今は内部で喧嘩してる場合やないやろ。愚痴や文句を言ってる暇があったら、もっと数字を追っかけなあかんやん。」
「でも、お言葉を返すようですが、数字を追いかけるのは、教育者としては違うと思うんですよね。」
「はあ?教育者?何やねん、それ。たかが、塾の先生やないか。それを教育者面しててどないすんねん。」
「いや、別に教育者面しているつもりはないんですが…。」
「だったら、つべこべ言わんと追いかけたらええがな。だいたいな、数字だけやのうて、運でも、成長でも、追いかけへん奴がそれらを手に入れることなんてできるわけないやん。良い授業をしてたら、数字はついてくる?…そんなことあらへんって。じっとしてるだけで運をつかめる?…そんなわけないがな。必死に追いかけている奴しか運は掴めへんって。成長だってそうやで。勉強もしてへん、努力もしてへん奴が成長なんてできるわけないやん。そんなん、小学生のガキんちょでも分かる話やで。」
「そ、そうかもしれませんが…。」
「ジブン、中居ちゃんやったっけ?」
「はい、中居です。」
「あんな、木村ちゃんのこと、いい加減な対応をしてるから退塾が多いって言ってたわな。」
「はい。」
「それはその通りや。」
「ええー!」
思わず、木村がズッコケた。
「だから、そのことを指摘するんはええわいな。傷のなめ合いをしてもしゃーないからな。でもな、そのことに気づいていて、中居ちゃんは木村ちゃんに何かアドバイスとかしてたんか?」
「いえ…。」
「だったら、偉そうに言えんやろ。ジブンの言い方は愛情の欠片もない単なる批判や。そんなもん、何の意味もあらへん。木村ちゃんの批判をする前に、まずは、そういうジブンの未熟さを見つめなあかんで。」
「あっ、はい…。すみません…。」
「次に、木村ちゃんか。」
「はい。」
「ジブン、稲垣ちゃんの批判をしてたわな。朝まで仕事せーみたいな感じで。それに、“必死さが足りん。もっと働け。”とも言ってたわな。」
「あっ、はい…。」
「確かに、稲垣ちゃんは働いてないわ。」
「ま、まじですかー!」
今度は稲垣がズッコケた。
「ただな、何で、朝まで仕事せなあかんねん。夜中に働いて生徒数が増えるんか?明け方まで仕事することが必死に働くちゅうことなんか?」
「いえ。ただ、やることはいくらでもあるわけですから…。」
「そんな仕事の仕方をしてるから、いつまで経っても生産性が上がらんねん。それに、夜中まで働かせて、何かあったら、ジブン、責任取れるんか?」
「いえ、それは…。」
「だったら、そんなこと言うもんやない。だいたい、仕事はダラダラするもんやないで。特に、これからの時代は、時間内でいかに効果を上げるかちゅうことが大事なんや。」
「はい。」
「ただ、こういう話をすると、すぐに人を増やさなあかんという発想になる奴がおるんやけど、それは違うからな。人を増やすことは生産性を上げることやないで。皆も分かってると思うけど、会社が潰れる一番の原因は人件費の高騰や。」
「はい。」
「だからや、一人ひとりの社員が頭を使って、工夫を凝らし、生産性を上げることを意識して、仕事をせなあかんのや。」
「あっ、はい…。」
「そういうことで言うと、草彅ちゃんもや。」
「はい。」
「中居ちゃんが娘のために休みを取ったこと批判してたわな。」
「はい。」
「確かに、中居ちゃんの娘は、中居ちゃんに似てブサイクや。」
「ひゃー、何てことをー!」
今後は中居がズッコケた。
「でもな、いくらブサイクでも中居ちゃんにとっては可愛い娘なんや。もちろん、草彅ちゃんの休みを取らずに頑張ろうという姿勢を批判するつもりはないで。」
「あっ、はい…。」
「ただ、よくよく考えてみ。何で家族を犠牲にせなあかんねん。そんな人生、虚しいやろ。可愛い娘、いや、ブサイクな娘の発表会に行ったってええやないか。だいたい、夜遅くまでとか、休みも取らずとか、そういう頑張り方はもう時代遅れやで。そんなことやってたら、それこそブラック企業とか言われるで。」
「あっ、はい。」
「まあ、もともとこの塾業界は、裏家業というか、真っ黒の業界やったんやけどな。世の中の塾人達の頑張りで、ちゃんとした職業として認知されるようになって、やっと日の目を見られるようになってきたのに、いつまでも昔の意識でやってたら、優秀な若い子らがこの世界に入ってこんようになるで。そんなことになったら、それこそ、この学習塾業界のお先は真っ暗やで。」
「あっ、はい…。」
「それからな、誰でも自分が思う正義を振りかざしたくなるもんやけどな、わし、そういうのはダサいと思うわ。それぞれの側に立った正義っていうもんがあって、唯一存在する正義なんてもんはない。いろいろな正義、いろいろな価値観を認めながら、やっていくのがこれからの仕事の在り方やで。」
「はい。」
「それから、稲垣ちゃんや。」
「はい。」
「草彅ちゃんのこと、いつも文句ばっかり言ってるくせに、良い子ぶってるって言ってたわな。」
「はい。」
「そうなんや。あいつは昔のアイドルみたいに、ブリブリぶりっ子や。それにガキんちょや。」
「ええー!その言い方!!」
今後は草彅がズッコケた。
「確かに、草彅ちゃんは他責性が強すぎるわな。もっと、“自分が源泉”ちゅうスタンスに立たな、人からの信用も得られんわな。それはそれで反省してもらわなあかん。でもな、稲垣ちゃんの教室はどうやねん。そんなにうまく行ってるんか?」
「いえ、それは…。」
「わしから見ると、草彅ちゃんの教室も稲垣ちゃんの教室も、目くそ・鼻くそや。ちなみに、草彅ちゃんの教室が目くそで、稲垣ちゃんの教室が鼻くそや。」
「えっ、そこ、どうでもよくないですか?」
「まあそうやな。どうでもええわ。とにかく、二教室ともたいして変わらんちゅうことや。はっきり言って、稲垣ちゃんの教室も雰囲気悪いで。」
「あっ、はい…。」
「だからな、人の教室のことをつべこべ言う前に、自分の教室を見直した方がええんと違うか?」
「はい…。」
「だいたい、皆、自分のことを棚に上げて、他人のことをとやかく言い過ぎるわ。“人のしり見て、我がしり直せ”ちゅう諺もあるやろ。レベルの低いこと言ってたらあかん。」
「すみません。ただそれを言うなら、“人のふり見て、我がふり直せ”ではないでしょうか?」
「まあ、そうとも言うわな。」
「いや~、そうとしか言わないと思うんですけど…。」
「稲垣ちゃん、ジブン、そういうところがあかんねん。」
「あっ、すみません!」
「それから、香取ちゃんや。」
「教室の雰囲気が悪いって言ってたわな。草彅ちゃんのことは尊敬できないとも言ってたわな。」
「はい。」
「勇気を出して、よう言ったな。」
「はい、有り難うございます!」
「でもな、香取ちゃん、それがあかんねん。」
「ええー!まさかのダメだし!!」
たまらず、香取がズッコケた。
「まあ、香取ちゃんの気持ちも分かるけどな、ジブン、部下力が低すぎやで。こんな場面で上司のメンツを潰したらあかんやろ。言いたいことがあるんやったら、事前に言っとかな。それにな、世の中には一杯ダメ上司がいるわ。そんな中で、上司をダメ上司にせんように動いていくんが部下の仕事や。そういう努力をしたんか?」
「いえ、不十分だったと思います…。」
「だったら、文句言う資格はないで。もっと、コミュニケーションを取って、上手くやっていかなあかん。それは上司だろうが、部下だろうが関係ない。これからの時代は、他人と信頼関係を結んで、協力していくという力が凄く大切なんや。」
「あっ、はい…。」
「最後に、我利ちゃんや。」
「はい、どんな批判でも受けます。」
「まあ、会社をやってると、いろいろ大変やな。」
「えっ?」
タヌーキの優しい言葉に拍子抜けをした我利は思いっきりズッコケた。
「確かに、社内がこんな感じになったのは社長である我利ちゃんの責任や。そこは反省せなあかん。でもな、頑張っている組織ほど、こうなるもんなんや。」
「あっ、はい…。」
「つまりな、どんな組織でも上手くいかんようになったら、皆のストレスが溜まって、犯人探しが始まるようになる。そして、そのことで社内の雰囲気がどんどん悪くなって、悪循環から抜け出せなくなり、最悪の場合、会社は潰れる。」
「はい。」
「だから、もうええやろ。解散したらええ!」
「えっ?!い、い、いま、何て言いました?」
「解散って言ったんやけど。」
「いやいや、簡単に解散なんて言わないでくださいよ!今まで皆で必死に頑張って来たんです。こんなことで終わりになんかしたくないです!」
「それがあかんねん。」
「えっ?」
「それにしがみついてるから何も始まらんねん。“解散”ちゅうのは、会社を潰せって言ってるんやない。今までの“個勉塾”を解散して、新しい“個勉塾”を創れって言ってるんや。」
「新しい“個勉塾”…ですか?」
「そうや。この“個勉塾”の社員は本当によく頑張ってると思うし、良い奴ばかりやと思う。」
「あんなにダメ出ししておいてですか?」
「おお。分かってるやろ?わしのダメ出しは愛の印や。分からん奴には、わしは何も言わんからな。アハハハ。」
「まあ、そうですね…。」
「ただな、このへんで我利ちゃんも、会社も変わらなあかんと思うわ。」
「変わる…ですか?」
「そうや。皆も耳の穴かっぽじって聞いといてや。」
「はい!」
「今、時代は大きく変わろうとしている。それは皆も分かってるやろ?」
「はい。」
「そんな中、その時代の波に乗れずに、変われない組織と人材は淘汰される。それは、この春の募集期で分かったやろ?」
「何がですか?」
「ジブンらの実力の無さがや。」
「実力の無さ…ですか…。」
「そうや。実際問題、退塾や入塾で苦労してるやろ?大手塾が出てきて、今までやってきたことが上手くいかんようになって来てるやろ?」
「はい。」
「まあ、そんなもんやで。ええか、ジブンら、勘違いしたらあかんで。今まで地域で一番の学習塾をやってきたことは認めるけど、我利ちゃんも含めてやけど、ジブンらの力なんて、たいしたことあらへんということを自覚せなあかん。」
「あっ、はい…。」
「今のジブンらの実力の範囲内でやってる限り、そのうち通用せんようになる。だから、自分の力はまだまだ未熟やということを認識して、もっと勉強せなあかんし、努力せなあかんねん。」
「はい。」
「今の時代、極力残業はせん方がいい。休みもしっかり取らなあかん。それは時代の流れや。そんなもんに抵抗してたら、それこそ時代に取り残されて淘汰されるやろう。」
「はい。」
「でもな、労働時間が短くなる分、逆に厳しくなったということを分かっとかなあかんで。今までなら、人の二倍働いて成果を出すこともできたやろう。ただ、これからは、それは通用せん。人の二倍頭を使わなあかんし、人の二倍勉強せなあかんちゅうことや。つまり、単に休みが多くなったことを喜んでたらあかんのや。休みの日に何をするか、どういう過ごし方をするかで、人生が大きく変わる。だから、本も読まなあかん。いろいろな所に行って、いろいろな体験をした方がええ。それやのに、本は嫌い、いろいろな所に出かけるのは面倒、そんなこと言ってたら、そんな人材は淘汰される。そういう時代に入ったちゅうことや。」
「はい。」
「そして、それは塾も会社も同じや。昔と同じ考え方や、やり方でやっている限り、必ず時代に淘汰される。変わるんやったら、今や、今しかない。だから。ここから新しい“個勉塾”を創っていかなあかんのや。」
「なるほど!」
「それでや、本題に入るわ。」
「ええー!!今までのは本題じゃなかったんですか!!」
今度は全社員がズッコケた。
※明日に続く
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田がお送りしました![]() 。
。