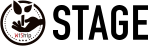二十二.“個勉塾”の解散?!
四月に入った。
春の募集期終了まで、あと一ヶ月。
“個勉塾”の退塾は三月に入って止まったかに見えたのだが、そうではなかった。
決して多くはないのだが、他塾に移籍するという退塾は断続的に出ていた。ちなみに、その他塾とは“天下一個別”だ。
やはり、“天下一個別”の営業ローラー作戦が功を奏しているのだろう。
問合せについても、紹介は出ているのだが、昔のような爆発力はなかった。
つまり、社員達が無理をして頑張っているにも関わらず“個勉塾”の業績はなかなか改善の方向に向かっていなかったのだ。
そして今日は“個勉塾”の全社員が集まる全体会議だ。
我利勉は、この会議で、社員達にどんな話をしたらいいのか迷っていた。
「この苦しい状況の中、タヌーキさんなら、彼らにどんな言葉をかけるんだろうか…。」
会議まではまだ時間がある。
「そうだ!もしかしたら、“からくり屋珈琲店”にタヌーキさんがいるかもしれない。行ってみるか。…いや、やっぱりダメだ。私はまたタヌーキさんに頼ろうとしている。ダメだ、ダメだ。」
我利は“からくり屋珈琲店”に行きたい気持ちを抑えて、別の喫茶店“ヨンジェルマン”で会議まで時間をつぶすことにした。
「う~ん…どういう話をしたらいいんだろうか…。」
その時、背後から声がした。
「そんなに暗い顔をして、どうしたのかな?」
「あっ!タヌー…」
「アハハハ。残念だったな、ミーはタヌーキではない!」
「あなたは、“天下一個別”の参謀のキーツネ!」
「バカもの!!ミーのことを呼び捨てにするな!」
「あっ、すみません。」
「ミーは個別指導の神様だ。神様に対して、そんな呼び方をしていると、バチが当たるぞ。いや、もう当たっているんだろうがな…ふふ。」
「くっ…。」
「キミは、確か、あの個人塾に毛が生えた程度のショボい塾・“個勉塾”の社長だったな。」
「別にショボい塾ではありません!」
「アハハハ。キミみたいなオーラの欠片もない人間が社長をやっていて、ショボくないわけがないだろう。」
「失礼な…。」
「ん?どうしたんだ?今日はタヌーキと一緒じゃないのか?」
「一緒じゃありません!」
「ふん!とうとうタヌーキにも見放されたのか?アハハハ。」
「・・・。」
「黙っているところを見るとやっぱり、図星か。情けない奴だ。」
「放っといてください!」
「まあでも、キミはタヌーキがいないと、自分の力では何もできないんだな。」
「・・・。(確かに、私はこの状況を打破できない情けない社長だ…。)」
「どうした?何も言い返さないのか?」
「いや…。」
「まあ、いい。ミーは別にキミに恨みがあるわけではない。」
「・・・。」
「それに、ここまでよく頑張ったと思うぞ。敵ながら褒めてやる。塾なんて簡単に作れるが、それを会社組織にして、十年以上やっていくのは大変なことだ。しかも、地域で一番の塾を守り続けるのは至難の業だ。でも、もういいだろう。楽になれ。」
「えっ?」
「ミーはキミの塾を潰そうとは思っていない。」
「それは、どういうことですか。ふざけたことを言わないでくださいよ!生徒数が減ったら、うちの塾は潰れるじゃないですか!」
「ん?何故だ?」
「だって、内部留保なんて殆どないし、借金だって一杯残っているし、生徒数が減って、売上や利益が減れば、社員達に給料を払えなくなるじゃないですか!」
「ふふ…。だったら、縮小すればいいだけじゃないか。」
「えっ?縮小?」
「そうだ。今ある教室を一つだけ残してキミともう一人の社員くらいでやればいいんじゃないのか。それなら、キミとキミの家族が飯を食うくらいは何とかやっていけるだろう。」
「いやいや、そんなことしたら、うちの社員達はどうなるんですか?」
「別にいいじゃないか。社員なんて、所詮は他人なんだから、そこまでキミが責任を負わなくてもいいんじゃないのか?まあでも、それが心苦しいのなら、キミのところのレベルの低い社員達を“天下一個別”で雇ってやってもいいんだがな。使い物になるかどうかは知らないが…アハハハ。」
「何ということを…。」
「我利君と言ったかな?キミは甘いな。その甘さが命取りになるぞ。」
「・・・。」
「まあでも、自分の人生だ。好きにしたらいいがな。ただ、これだけは最後に言っておいてやろう。」
「何ですか?」
「組織というものがダメになるのは、外敵によるものではない。何だと思う?」
「分かりません。」
「それは、自滅だ。社員達の心が乱れ、組織が乱れ、内部崩壊が起きる。」
「な、な、内部…崩壊…。」
「そうだ。そして、それはもう目の前だ。アハハハハ。」
「うちの社員達に限ってそんなことは・・・。」
「そうかな。まあ、楽しみにしておくんだな。じゃあ、せいぜい頑張りたまえ。」
※明日に続く
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田がお送りしました![]() 。
。