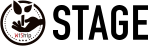十五.第七ラウンドの終了
十二月に入った。
第七ラウンドでは、“天下一個別”も“個勉塾”も、死力を尽くして“二学期末のテスト対策”を行った。
十一月に行われるテストが一年間で一番大切だという説があるが、そのことは両軍ともによく分かっていたからこそ、お互いに必死だったのだ。
今回、“天下一個別”は、AIを使った教務システムで、普段の授業の精度を上げ、テスト前には“個勉塾”がやっていることと同じレベルでテスト対策イベントを実施し、かたや、“個勉塾”はというと、今までやってきたテスト対策の枠組み自体は変えてはいないが、テスト二週間前からのテスト勉強計画面談に力を注ぎ、子ども達のテスト勉強に対する意識や取り組みを変えていく作戦で対抗したのだった。
その結果、成績向上という観点からは、若干“天下一個別”に分があったのだが、生徒数増という観点から見ると、やはり“個勉塾”の方が勝っていたのだ。
果たして、この結果が意味するものは何なのだろうか?
成績向上率の高さから、今後、“天下一個別”の勢いが増し、生徒数が伸びていくための土台を築いた結果だったと言えるかもしれない。
それとも、このテスト対策の時期に、生徒数が伸びたのが“個勉塾”だと考えると、“個勉塾”のテスト対策のやり方の方が顧客に支持されたと言えるのかもしれない。
いずれにせよ、その答えはこの十二月や来春の募集期に表れて来るのだろう。
■場面は、“天下一個別”の本社ビル内。
会議室で、いつものように、参謀・キーツネと営業本部長の塩川が話をしていた。
「キーツネさん、我が“天下一個別”の生徒たちの今回のテスト結果は上々でしたよ!」
「そりゃあ、そうだろう。」
「はい、我々も相当気合いを入れて臨みましたから、してやったりという感じです。」
「まあ、キミたちの頑張りもあっただろうが、やはりAIの教務システムで普段の授業の質が向上しているのも大きいんじゃないか?」
「それは、そうです。あのシステム、かなり優れものですからね。」
「ふふふ。」
「ただ…。」
「ただ、何だ?」
「はい、生徒数の伸びとしては、イマイチでして、今回も“個勉塾”に負けています。」
「えっ!何だって!」
「す、すみません!」
「う~ん…我々よりも成績向上率の低い“個勉塾”の方が、生徒数が伸びているとは、いったいどういうことなんだ…。」
「キーツネさん、たぶん、あれですよ。」
「あれとは?」
「はい、まだまだ我々の凄さが地域に浸透しきっていないだけだと思うんですよね。テスト結果が全部揃ったのは十一月末でしたしね。」
「ん?つまりは、今回のテスト結果が生徒数に反映されるのは、これからだと言いたいわけか?」
「そうです。今回の結果で、やっと地域の人々が我々に目を向け始めた段階だと思いますので、これから爆発するんじゃないかと。十二月はたっぷりチラシも入れてますしね。」
「なるほど。塩川君の言うことも一理あるかもしれないな。」
「はい、一理も二理も三理もあると思います。」
「いや、一理しかない!」
「またまた、そんなはっきりと…ほんと、意地悪なんだから~。」
「塩川君、ミーに馴れ馴れしい話し方をするな!」
「あっ、はい。失礼しました。」
「いいか、塩川君、キミのように楽観的な見方をしていると、塾運営は上手くいかないぞ。」
「えっ?」
「だって、今までもそうだっただろう。これで大丈夫だと思っていても、いつも、あの“個勉塾”にやられてきたじゃないか。我々は何度も同じミスを犯すわけにはいかない。塩川君、もっと、危機感を持て!」
「あっ、はい!でも、お言葉を返すようですが…。」
「何だ?」
「どうやら、“個勉塾”は我々に比べれば、そんなにテストの点数は上がっていないようで…。」
「その根拠は?」
「はい、うちに来ている生徒がそう言っていましたし、私の長年の塾屋としての勘とでも言いますか…。」
「キミはバカか!一人の生徒の話やキミの勘なんてあてになるか!ほんと、キミとコンビを組むのは、私にとってはストレスしかない。」
「はい、すみません。」
「ミーは、キミのそういう単細胞で、能天気なところが、嫌いなんだ。いいか、ミーの方程式では、この十一月もテスト対策の勢いで、我が“天下一個別”の生徒数はぐーんと伸びるはずだったんだ。それが、そうなっていない。」
「はい、それは事実です。」
「そうだろ?塩川君、“個勉塾”にあって、ミー達にないものは何だと思う?」
「う~ん…それはないですね。我々の塾は、彼らが持っているものは全てあると思います。資金力やブランド力だって我々の方が上ですし、様々なシステムにしても、彼らには手が届かないレベルで揃っています。」
「確かにな。」
「それに、人材レベルだって、段違いだと思うんです。」
「まあ、普通で考えるとそうだが、キミを見ていると疑問に感じることもしばしばだが。」
「またまた、ご冗談を~。」
「冗談じゃない。真面目にそう思うんだ。」
「そ、そうですか…。」
「じゃあ、やはり、タヌーキとミーの戦略の差なのだろうか。あいつは、学生時代もできそこないだったくせに、ここぞという時には力を発揮してくる。何とも分からない奴だ。」
「そうですか。」
「まあ、考えていても仕方がない。奴には思いつかないような戦略で勝負してやる。ミーを舐めると怖いということを思い知らせてやるんだ。」
※明日に続く
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田がお送りしました![]() 。
。