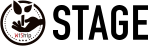■場面はタヌーキと我利サイド。
タヌーキがトイレに行っている間、我利勉は何かロボットに対抗する手段はないものか考えていた。
「あ~、すっきりしたわ~。」
「それは良かったですね。」
「何や、ジブン、辛気臭い顔してるけど、何か悩み事でもあるんか?」
「悩み事でもあるんかじゃないでしょうが!さっきから、相談しているじゃないですか!」
「ん?」
「ロボット対策ですよ!」
「ああ、あれね。まだ考えてるんかいな。」
「当たり前でしょ!こっちは本当に困っているんだから、タヌーキさんもちゃんと考えてくださいよ!」
「そうやな~。我利ちゃんさあ~。」
「はい。」
「個別指導塾の商品って何やと思う?」
「それは…講師と言いたいところなんですが、今の時代は教材だとか“天下一個別”のような教務システムなんかも重要で、むしろそっちの方が商品と言えるものなのかもしれませんね。」
「そんなわけないやん。どこまでいっても塾の商品は“講師”に決まってるやん。」
「えっ?!」
「だってそうやん。どんな教材を使おうと、完璧な個別カリキュラムを作ろうと、肝心要の生徒の心を動かさん限り、成績なんて上げられへんわけや。」
「まあ、そうですけど…。」
「ほんで、その生徒の心を動かすんは誰や?教材か?カリキュラムか?それともAVロボットか?」
「最後のはAVじゃなくてAIですけど、いずれにしても、それらは違いますね。やっぱり“講師”しかあり得ないですよね。」
「そうや。教材も個別カリキュラムも確かに重要や。AVもあった方がええやろ。」
「AIですけど…。」
「でもな、それらは全部メインの商品やない。」
「えっ?無視ですか…。」
「は?何?」
「いえ、何でもないです。」
「だからな、“天下一個別”が訳の分からんイヤラシイもんをメイン商品にして勝負してくるんやったら、こっちは最強の商品の“講師”で対抗したったらええだけやん。」
「最強の商品?」
「そう、ロボットやない“血の通った人間”の講師たち。奴らの情熱や。個別指導塾の商品はこれ以外にはあり得へん。」
「う~ん…そうかもしれませんけど、さっきも言ったように、相手はAIを使った凄い商品を投入してくるわけですよ。講師の強化くらいじゃ勝てないんじゃないですか?うちも、もっと強力な商品を考えなきゃ…。」
「そんなんいらん!もちろん、金があって何か凄いもんを導入できるに越したことないけど、ジブンとこ、貧乏塾やで。金が無いんやったら、知恵とハートで勝負するしかないやん。」
「う~ん…そうですけど…。」
「それにな、何かジブン、勘違いしてへんか?」
「何がですか?」
「生徒数増やすんも、大手塾に勝つんも、何か特別な武器がいると思ってへんか?」
「そりゃあ、まあ…。」
「それが違うねん。生徒数増やすんに飛び道具なんてあらへん。やるべきことを、どれだけきっちりやれるかが一番の肝や。」
「あっ、はい…。」
「だからな、個別指導塾ちゅうのは、“講師”をどれだけ活性化できるかにかかってるわけや。それで勝敗がつくと言っても過言やない。ここがダメやと何をやっても上手くいかんで。」
「確かに…。」
「それやのに、キーツネたちは講師たちを単なるコマとしてしか扱ってへん。講師にしっかり挨拶させて、コミュニケーションと取らせて、ホルスタインかなんか知らんけど、そういう形だけ強化したらええと思ってるふしがあるわ。」
「あの~。」
「何や?」
「ホルスタインというのは乳牛の品種の一つのことで、ホスピタリティのことかと…。」
「ジブン、ほんと、いちいちうるさいわ。そんな細かいことは何でもええがな。」
「何でもよくはないと思うんですけど…。」
「うっさい!」
「あっ、すみません…。」
「わし、気分悪くなってきたわ。」
「ほんと、すみません。でも、タヌーキさんの仰りたいことはよく分かりました。で、具体的にはうちの商品の講師達をどう強化したらいいですかね。」
「そうやな~。もっと教室運営にも巻き込まなあかんし、もっとこの仕事にのめり込まさなあかんな。」
「巻き込むことと、のめり込ますことですか…。」
「何やショボンとして。何も難しいことやあらへんで。」
「いや~、言葉で言うのは簡単ですが、実際にそういうふうに持っていくのは、なかなか難しいことだと思うんですけど…。」
「そんなに難しく考えんでええ。」
■場面はキーツネと塩川サイド。
夜の七時に講師達が教室に集められ、教務システム導入のための講師研修会がスタートした。
まずは、キーツネが講師達に話をし出した。
「いいか、講師諸君、今後はこのAIを使った教務システムを活用して指導してくれたまえ。これは我が社が開発した最高のシステムなんだ。」
その時、一人の講師が手を上げた。
「すみません、質問してもよろしいですか?」
「君!やめなさい!」
塩川は、即座に講師からの質問を遮ろうとした。
「いや、塩川君、構わないから質問させてあげなさい。」
「あっ、はい。」
「では、少しお聞きしてもいいですか?」
「どうぞ。」
「この教務システムの指示通りに指導すればいいということでしたが、今後は私達が一切判断してはいけないということでしょうか?」
「まあ、そういうことだ。」
「それでは私達としては楽しくないというか…。」
「キミたちの楽しさって何だ?担当生徒の成績を上げることではないのか?」
「それはそうですが…。」
「だったら、人間の判断よりも、AI…つまり人間の頭脳を超える人工知能の判断を信じて指導する方が、成績が上がる確率が高まるのではないのか?」
「確かに仰る通りですが…。」
「いいか、講師という仕事はたかがアルバイトかもしれないが、されどアルバイトだ。お金をもらっている以上、結果を残さなければならない。自分の感情よりも結果を優先させる。それが仕事というものだ。」
「あっ、はい…。」
「まあ、キミらにもいろいろな想いはあるだろう。しかし、これは会社方針だ。それに従ってくれ。」
「あっ、はい、分かりました。出過ぎたことを言いまして、申し訳ありませんでした。」
「いや、分かってくれればいい。じゃあ、他に質問はあるかい?」
全ての講師がキーツネの話に納得したのかは分からないが、これ以上の質問は何も出なかった。
「じゃあ、次に生徒数目標の話をします。」
塩川が話をし出した。
「我々はこの地域で一番の個別指導塾を作り上げるつもりです。その為には、皆の力を借りなければなりません!具体的には十二月末までの生徒数目標は九十名です。つまり、あと三か月で約三十五名の生徒をゲットしなければならないのです。ですから、講師諸君は担当生徒から紹介を促してほしい。もちろん、今回も一名の紹介につきインセンティブを支払います。この秋冬のインセンティブ額は、な、な、なんと!三万円!!!」
講師達の顔付きが明らかに変わった。
「えっ?!そんなにもらえるんですか?」
「そうだ。だから、皆、はりきって頑張ってほしい。」
「分かりました!」
講師達は一斉に返事をした。
「うむ、うむ。これで上手くいくはずだ。」
※来週月曜日に続く
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田がお送りしました![]() 。
。