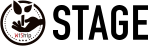五.第二ラウンドの終了
四月末で春の募集期が終了した。
第一ラウンドで劣勢だった“天下一個別”は、第二ラウンドでは、問合せの電話対応のプロ集団・コールセンターの社員や、社内で最も面談入会率の高い社員を集め、攻勢に打って出たのだが、最終的には、生徒数は三十名にも届かない二十九名という結果に終わった。
この数字は“天下一個別”史上、「最悪の立ち上げ」を意味するもので、実際、目標生徒数は五十名だったので、惨敗と言ってもいいだろう。
そう、またしても、“天下一個別”は、個人塾もどきの“個勉塾”にしてやられたのだった。
(五月のゴールデンウイーク明け)
■場面は“天下一個別”の本社ビル内。
「くそっ!個勉塾め!!!ちんけな個人塾の分際で、生意気な!!!」
「塩川営業本部長、どうされたんですか?そんな大きな声を出されて…。」
塩川の部下、霧島が話しかけてきた。
「どうしたも、こうしたもない。あのクソ個別塾、私に恥をかかせやがって!」
「あのクソ個別塾って、噂の“個勉塾”のことですか?」
「そうだ。あの塾のおかげで、私は、“天下一個別”の本部長会議で皆から笑われることになったんだ!くそっ!」
「そうでしたか…。でも、世界最高峰の参謀・キーツネさんの戦略を持ってしてでも、なかなか攻略できないとは、相当厄介な塾ですね。」
「いや、そうとも限らない。むしろ、キーツネの戦略に問題があるのかもしれない。」
「何だって?」
「だから、キーツネの・・・。」
塩川の目の前には個別指導の神様・キーツネが立っていた。
「あっ、いや、キーツネさん・・・。」
「キミ、何だかミーの悪口言ってたよね?」
「いえ、そんなことはありません!」
「じゃあ、ミーのこと、キーツネって呼び捨てにしてたよね?」
「いえ、とんでもありません!何かの気のせいだと思われます…。」
「そうか。おい、そこの社員君!」
キーツネは塩川の横にいた霧島に声をかけた。
「あっ、はい、私でございますか?」
「そう、キミ。」
「はい、何でしょう?」
「今さぁ、塩川君がミーのこと呼び捨てにしていなかった?」
塩川は、とっさに霧島に目配せをした。
「はい、そんなことはなかったかと…。」
「本当か?」
キーツネは鋭い眼光で、霧島のことを睨み付けた。
「いえ、すみません!塩川営業本部長はキーツネさんを呼び捨てにしておられました!」
「はあ?!霧島!お前はバカか!何ですぐに寝返るんだよ!」
「バカなのはキミだ!塩川君!」
「キーツネさん、申し訳ありません。ついつい、ノリで…。」
「ノリって…。やっぱりキミは単細胞で、どうしようもないポンコツだ。ほんと嫌いだ…。」
「すみません!」
「まあ、いい。でも、これだけは言っておくが、ミーの戦略は間違っていなかった。」
「あっ、はい…。」
「それなのに、この結果だ。塩川君は何故だと思う?」
「はい、さっぱり分かりません!」
「やっぱり、キミに聞くだけ無駄だったな…。いいか、今回の敗因は、二つある。」
「はい。」
「一つは、ミーの予想以上にキミのパフォーマンスが悪かったこと。」
「はい、申し訳ございません…。でも、私はキーツネさんの指示通りに動いたまでで。」
「ほ、ほ~ん、やはりミーのせいだと?」
「いえ、そんなことは言ってはいませんが…。」
「だったら、ミーのカンに触るようなことを言うな。」
「はい、すみません。」
「もう一つの敗因は、向こうの戦略が勝っていたことだ。」
「はい…。」
「でも、前にも話をしたと思うが、ミーには、あの我利という男にそんな頭脳があるとは思えないんだ。だから、向こうの参謀はかなり優秀な奴かもしれない…。塩川君、向こうの参謀とやらの正体は分かったか?」
「いえ、いろいろ探ってはいるのですが、全く分からないんです。ただ…。」
「ただ、何だ?」
「“個勉塾”の代表の我利という人物はどうやらペットを飼っているようでして、よくパフェを食べさせているようなんです…。」
「えっ?ペットだって?」
「はい、それが犬や猫じゃなくて、何と!タヌキなんですよ!アハハハ、センスないでしょ!」
バコーン!!
「痛っ!キーツネさん、何故、いきなり殴ったんですか?」
「キミは本当にバカか!その情報はいつから知っていたんだ?」
「えっと…だいたい一ヶ月前くらいですかね。」
「はあ…。ほんと、キミは究極の役立たずだ。」
「キーツネさん、そんな血相を変えて、いったいどうしたんですか?」
「そのタヌキは、タヌーキだ。」
「ん?タヌキ?タヌーキ?意味が分かりません…。」
「だからタヌキに似た個別指導の神様のタヌーキだと言っているんだ!」
「ひゃー!あのタヌキも個別指導の神様だったんですか!!!」
「そうだ。あいつはただものじゃない。」
「えっ?キーツネさん、そのタヌキのことをよく知っているんですか?」
「タヌーキは、ミーの神様大学時代の同級生だ。」
「えっ!!!キーツネさんの、ど、ど、同級生ですか!」
「そうだ。成績はいつもミーが主席で、タヌーキはドンケツ。」
「だったら、全然、勝負にならないんじゃないですか?」
「確かにそうなんだが…。」
「キーツネさん、どうかしたんですか?険しい顔をされていますけど…。」
「あいつは確かに大学では落ちこぼれだった。性格も悪かった。そして、変態だった…。しかし、昔からあまりにも非常識過ぎて、誰も奴の行動が読めないんだ。」
「えっ?キーツネさんもですか?」
「そうだ。それに、何故なのか分からないが、あいつには不思議な力がある。」
「そ、そ、それはどんな力なんですか?」
「まあ、そのうち分かるさ。」
「そうですか…。」
「ただ、塩川君、タヌーキが“個勉塾”についていると分かった以上、我々も警戒して戦いに臨んだ方が良さそうだ。」
「あっ、はい…。」
「じゃあ、いよいよ勝負の五月決戦に入るとするか!」
「えっ?勝負の五月決戦?」
「ん?キミは何をキョトンとしてるんだ?」
「はい、五月と言えば…」
「もしかして、何もできないとでも思っているのか?」
「ええ、通常は一息つく月と言いますか、特に何もしないのが普通でして…。」
「だから、キミはいつまで経っても三流止まりなんだ。」
「でも、私、こう見えても、関東ではバリバリ業績を…。」
「それは、この前、聞いた。」
「でしたら、三流というのは、ちょっと厳しい評価じゃないですかね?」
「シャラップ!黙れ!結果が全てだ!今回の立ち上げ時の失敗、恥を知れ!」
「はい!すみません!」
■場面は変わって、居酒屋“利三”。
「タヌーキさん!今日は乾杯といきましょう!」
「何や?上機嫌やないか。」
「はい、今年の春の募集期は大爆発で、生徒数もぐんと伸びたんですよ。何だか、全てが上手くいったので、嬉しくて嬉しくて…。ましてや、今回ばかりは“天下一個別”の進出で、ヤバいと思っていましたから、ホッとしてるんですよね。」
「そうかいな。まあ、それは良かったわな。」
「はい、これもタヌーキさんのおかげです。」
「まあ、わしは別にたいしたアドバイスはしてへんで。」
「いやいや、ご謙遜を。」
「まあな、確かに謙遜やけどな。わしがいなかったら、ジブンの塾、あかんかったと思うわ。間違いなく潰れてたで。」
「はあ?そんなふうに言われると、ちょっと違うと思うんですよね。」
「何がや?」
「今回みたいに上手くいったかどうかは分かりませんが、うちの社員達も力をつけてきましたから、潰れはしませんよ。」
「いや、潰れてたはずや。」
「潰れてませんって!」
私達の口撃は、お互いにエスカレートしていった。
「このボケが!オーラもないくせに、偉そうに!」
「何ですって!このクソ神様が!姿がタヌキそっくりでキモいんですよ!」
「何やて!われ、やんのか!」
「ええ、やりますよ!やってやりますよ!」
その時、店員が二人に声をかけた。
「お客様、他のお客様のご迷惑になりますので、静かにしてください!」
「あっ、すみません…。」
「おっ、ごめんちゃい…。」
私もタヌーキもばつが悪くなり、そそくさとその居酒屋を後にした。
そして、私達はいつもの“からくり屋珈琲店”に移動したのだ。
※明日に続く
オーラのないマッチメーカーこと、株式会社WiShipの岡田がお送りしました![]() 。
。